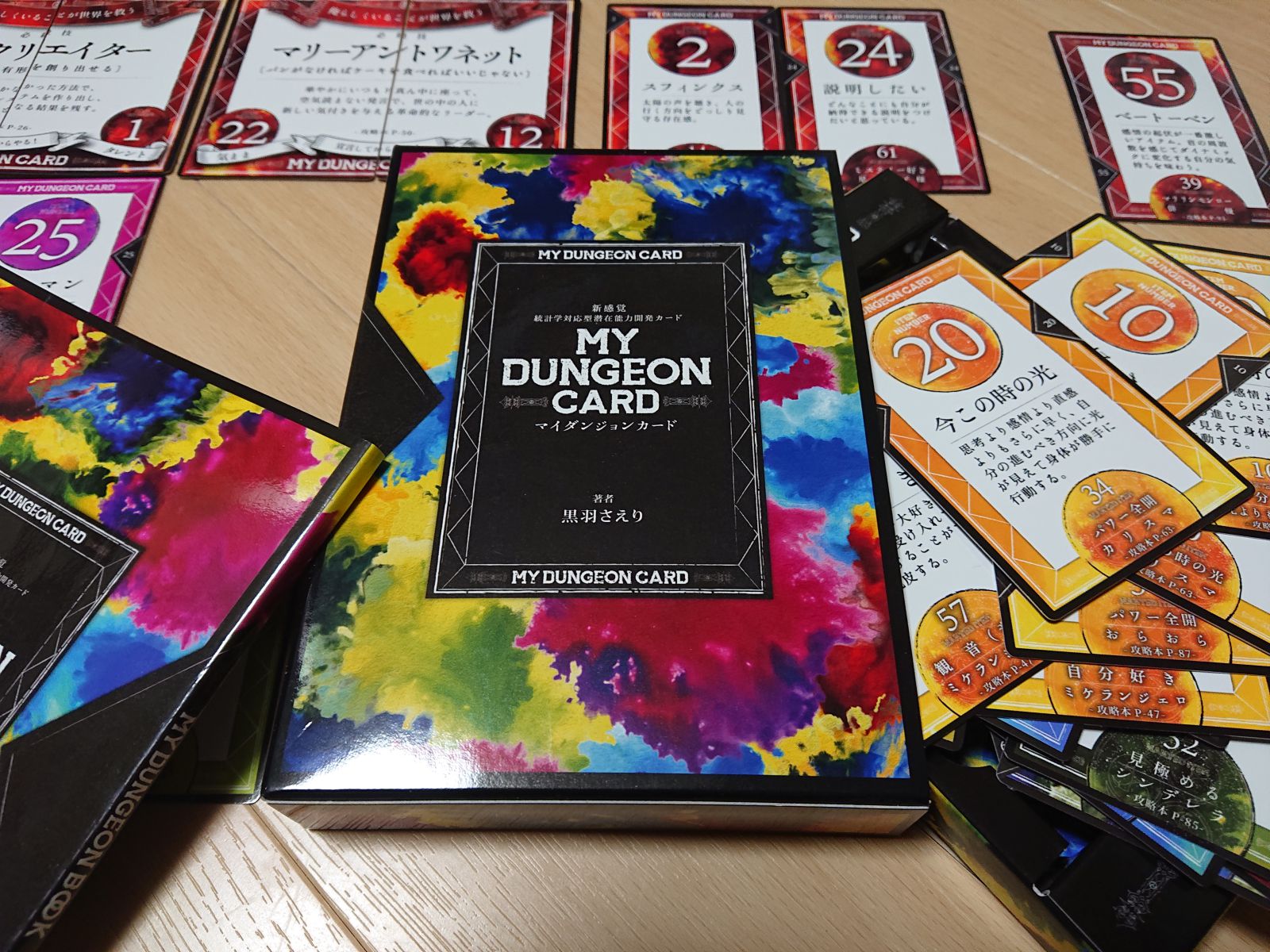こんにちは。
いちや です。
前回に続き、ヒューマンデザイン・ジャパンの登録者向け
公式コミュニティ(zoom作業部屋)からのお話です。
私のお気に入りのゲートの一つに、29番ゲートがあります。
それは、「はい」と言うゲート(原文:Saying Yes)。
何故かっていうと。私の極めて個人的な、
何となく感覚的で言ってしまうことに、恐縮ではあるのですが、
日本の文化に根ざしているなあと。
いい意味で、昭和なレトロな雰囲気に感じるから。
元気よく、はい!と返事をして、物事に取り組む。
よろこんで!といって、物事に取り組む。
そこには純粋さというか、一途な想いを感じてしまうからです。
ところで、原文の「Saying Yes」といえば、
CHAGE and ASKAの、「SAY YES」という楽曲を思い浮かべます。
1991年夏。テレビドラマ『101回目のプロポーズ』の主題歌です。
80年代を代表する楽曲だと思いきや、
大ヒットしたのは、こちらのドラマ主題歌がきっかけなんですね・・。
そして、武田鉄矢さん演じる達郎が、ダンプカーを目の前にして、叫んだ
「僕は死にましぇん」が、流行語大賞(大衆部門)にもなりました。
振られても振られても、結果にコミットしていく。
もちろんフィクションではあるのだけど、
29番ゲートの一面を垣間見ているように思えるのです。
これだと思ったら、一途にチャレンジしていく・・・。
そこには現世利益とか損得勘定は脇に置いているのだと。
そう感じるのです。
目には見えないけど、根気、忍耐が内在している。
最後までやり遂げる。成功するまで諦めない粘り強さ。
「はい!」と一度決めたことに深くコミットしていく。
話が飛んでしまったので、元に戻しましょう。
ヒューマンデザインの公式テキスト「Rave Cartography」では、
29番ゲートは、『「はい」と言う』(原文:Saying Yes)です。
一方で、「The Definitive Book of Human Design」という、
権威あるヒューマンデザインの入門書があるのですが、
ここには、忍耐(perseverance)と表現されていたのです。
(ちなみに、前述の書籍は、邦訳はされていません。)
そして、他でも、忍耐(perseverance)へと置き換えられている、
事例があるそうなのです。
公式に認定された講座で、学んできた人たちにとって、
64あるゲートの、たとえ一つであっても、その見出しの解釈が異なると、
当然のことながら、
「どっちが本物なの?」ということになりそう(笑)
先ほども触れましたが、29番ゲートを深掘りしていくと、
「“はい”といって結果にコミットする」ことと、「忍耐、根気」は、
実は、根っこの部分で、同じことを指し示しているんだなあ。
ということが分かってきます。
つまり、“はい!”といって結果にコミットしていくことは、
そう易々と、成し遂げられる訳ではなく、
「忍耐、根気」が伴うものだからです。
なので、今回の件に関していうと、決して誤りではないのです。
あくまでも、29番ゲートを「異なる角度から見ている」ということ。
本来の東洋の易経の解釈に近いのかも知れません。
公式なテキスト(いわゆるバイブル)で、『「はい」と言う』(原文:Saying Yes)
である以上、まずは、大元の原文を学ぶことが大切なのかなあと。
その上で、自分自身がしっくりくる解釈や言換えをしていく。
その際には、原書では○○だけど、私は□□だと解釈しました。とか、
他者へ伝えるときは、ひと言付け加えることが必要になってくるのかなあと。
今回の件を通じて、改めて感じたのです。
例えば、The Complete Rave I’Ching(レイブ易経)にしても。
原書の内容はとても抽象的な表現です。
邦訳でさえも意味や解釈が、スッと頭に入ってこないのです。
そこで、少しでも理解したい。
理解を深めたいと思って、様々な人から学んでいく。
あるいは、様々な人が書き記したブログなり、書籍を読んでいく。
新たな視点から解釈したもの。たしかに、分かりやすいし、
「腹落ちする方がいいのでは?」そう思われるかもしれません。
ここで気になること。
それは、教える立場の人の視点、フィルターを通して学ぶわけですが、
知らぬ間に、どんどん拡大解釈されていく可能性があります。
「はたして、その内容、解釈は、的を射ているのだろうか?」
なにしろ、ラーは、もうこの世にいないのだから、
確かめようがないのです。
最もやっかいなことは。
ラーの視点、フィルターを通した内容は、実は誤っていて、
「本当は、こちらの私の解釈が正しいです。」という人が現れてきたら?
不安がよぎります。
心地よく、心に染みこむ。
ラーの抽象的な表現よりも、納得感があるから。
時代と共に、それは避けられないことなのかもしれません。
ラーはあえて抽象的な表現のままで、書き記したのでしょう。
何故なら、「大いなるもの」から得たものが、まさに抽象的だったから。
懇切丁寧に理解しやすい言葉で得ていなかったから。
出来る限り、純粋なままで伝えたかったのでしょう。
あえて「超訳」はしなかったのです。
結果として、まるで暗号のような、謎解きのような文脈になったのだと。
あるいは、言葉で、理屈で理解させるのではなく(何かの先入観をもつことなく)
心に、身体に染みこませようと意図したものかもしれません。
だからといって、その“教える立場の人”の視点、解釈を
批判や軽蔑するつもりは全くありません。
何を信じても良いのです。その事に、良いも悪いもないからです。
私自身も、何だかんだ言いながらも、納得感を得たいですから、
場合によっては、同じように同調することもあるでしょう。
最後に、今回、私がとくに印象的だったエピソードがあります。
それは、ラーが生前、欧米で講義をしていたときに、
折に触れて語っていたという、嘆きの言葉です。
ボイス(大いなるもの)から伝えられたのは、この私なのに、
何故、私がありのままに伝えたことが、
「誤っている」と、言われてしまうのだろうか・・・。
何故、そうなってしまうのか私には理解できない。
とても悲しい。と。
マニフェスターのオーラ全開で醸し出された雰囲気。
さぞかし強烈だったのではないでしょうか・・・。
後日談として、先の29番ゲートの解釈の件。
忍耐(perseverance)から、「はい」と言うゲート(原文:Saying Yes)へ
本来の解釈に戻されたそうです。
それにしても、第三者からの立場からみていくと、
全くヒューマンデザインに触れたことのない方は、
29番ゲートが、「“はい”と言う」ゲートです。
というよりも「忍耐・根気」のゲートです。と、
説明された方が、しっくりくることは否めません。
でも、だからこそ、「“はい”と言う」言葉の言い回しに、
強いメッセージ性を感じてしまうのです。
私だけでしょうか。
あなたはどう感じますか。